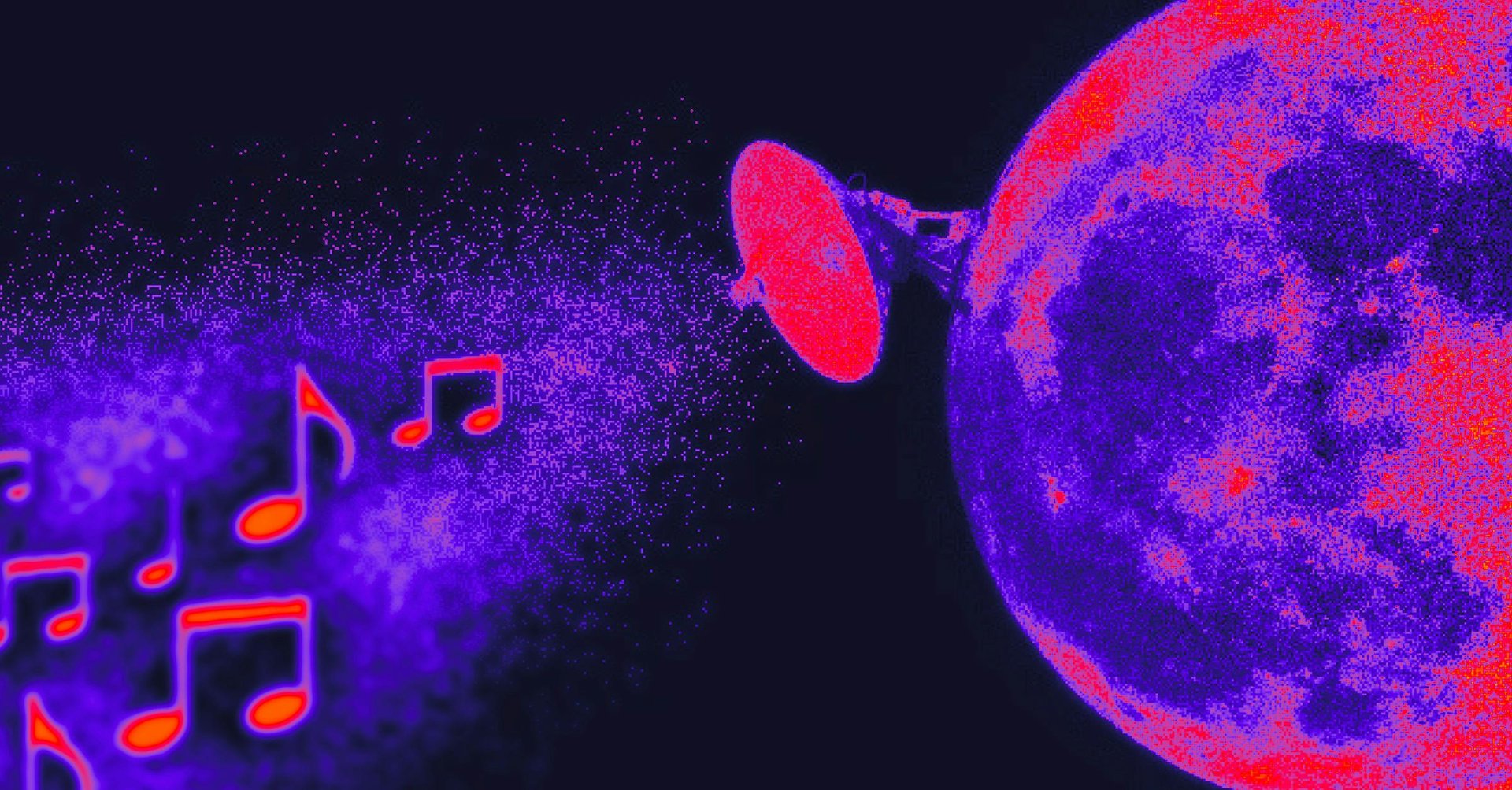音楽プロモーション2025|最新の広め方ガイド
音楽を正しい方法でプロモーションすることが、これまで以上に重要になっています。
幸いなことに、かつてのように大手レーベルの後押しがなくてもメインシーンに出ることは可能です。
音楽プロモーションの最大の前提は、言うまでもなく自分らしさを表現した良い楽曲を作ることです。独立して活動しながら成果を出すには、ブランディング、SNS活用、配信サービス上でのプロモーション、ネットワーク作りを組み合わせる必要があります。
ファン層を広げるには、多角的なスキルを持ち、SNSに精通し、自分のジャンルに自信を持って発信できる力が求められます。さらに多くのコンテンツを発信することも不可欠です。はっきり言って、膨大な努力と継続的な取り組みが必要です。ただし、自分の音楽を信じ、覚悟を持って取り組めば、必ずファンを見つけ、キャリアを成長させることができます。
それでは、2025年に音楽をプロモーションする方法を見ていきましょう。
1. ストリーミングサービスに楽曲を配信する方法
ストリーミングプラットフォームは、人々の音楽の聴き方を大きく変えただけでなく、アーティストが楽曲をプロモーションする方法も変えてきました。今では、リリース予定の楽曲や既存のカタログをストリーミングサービスで広めるためのプランを持つことは、規模の大小を問わずすべてのアーティストにとって欠かせません。これは、ストリーミングからの収益が、楽曲再生やグッズ販売、コンサートチケットなどを通じて音楽を収益化する重要な手段の一つだからです。
さらに、これらのプラットフォームは、プレイリスト、音楽メディア、アルゴリズムによるおすすめなどを通じてファンが新しい音楽を見つける場所にもなっています。
楽曲をストリーミングサービスに配信するためには、配信代行サービスを利用する必要があります。
LANDRディストリビューションは、多様なプランを提供している優れた選択肢のひとつです。
2. 強いオンラインプレゼンスとブランドを築く
SNSやオンラインでの存在感がこれまで以上に重要になっている今、自分自身と音楽をどのように世の中に見せていくかを考える必要があります。
簡単に言えば、コンテンツを見た瞬間にリスナーが「これはあなたの音楽だ」とわかる状態を目指すべきです。ファンのフィードに投稿が流れたり、コラボ相手がストーリーをリポストしたりした時に、一貫した美学やスタイルがあれば、音楽はより記憶に残りやすくなります。もちろん、ブランドアイデンティティを確立するには時間と熟慮が必要です。アーティストとしての活動全体に関わってくるからです。
ブランドを形作る主な要素には、アーティスト名やロゴ、使用するフォント、SNSでの文章のトーン、ビジュアルの見せ方、どんなコラボ相手やアーティストと関わるかなどが含まれます。憧れのアーティストがSNSでどのように自分を表現しているかを観察してみてください。どんなフォントを使っているのか? ビジュアルにどんな工夫をしているのか? 誰とつながっているのか?
常にブランドを意識し、音楽プロモーションを一貫したサウンド・メッセージ・ルック&フィールのもとに展開することが大切です。
音楽プロモーション戦略を構築する
経験豊富な音楽業界の専門家のサポートを活用しましょう。ブランド作り、SNSプレゼンスの構築、PRキャンペーンの企画、理想的なアルバムリリースの計画などをサポートします。
3. TikTokとInstagramに楽曲を配信する
TikTokは音楽とSNSの関係を大きく変えた存在です。もはや短い動画を投稿するためのアプリにとどまらず、アーティストが楽曲を広めるための主要なプラットフォームへと進化しました。テーマ性の強い曲、エネルギッシュな曲、あるいは懐かしいサウンドを持つ楽曲は、クリエイターが動画に使うことでバイラルヒットとなりやすく、瞬く間に拡散されます。Cordeliaの「I Think I Like This Little Life」、Drakeの「Nonstop」、Paul Ankaの「Put Your Head On My Shoulder」なども、クリエイターによる活用をきっかけに大ヒットしました。
ストリーミングサービスと同様に、デジタル配信代行サービスを利用すれば、誰でもTikTokやInstagramなどのSNSで自分の楽曲をクリエイターに使ってもらえるようにできます。
さらに、配信代行サービスを通じて楽曲やコンテンツのIDシステムを利用すれば、音楽が使われたりストリーミングされたりするたびに収益を受け取れる仕組みを整えることも可能です。
TikTokとInstagramに音楽を配信する方法をさらに詳しく見る
4. ストリーミングプロフィールを申請してプレイリストに載せる
ストリーミングサービスに楽曲を配信するのは第一歩にすぎません。
より多くのリスナーに届けるには、各プラットフォームごとにプロモーション戦略を立てる必要があります。
配信後は、Spotify for ArtistsやApple Music for Artists(希望すればTidal、Amazon、YouTubeも)でプロフィールを申請しましょう。プロフィールを持つことで、アーティストページにバイオや写真を追加できるほか、Spotifyでは新曲をエディトリアルプレイリストにピッチする機会も得られます。カスタムプレイリストやライブ予定の掲載なども可能になり、リスナーにより魅力的に音楽を届けられます。Spotifyの主要なエディトリアルプレイリストに掲載されることは、アーティストにとって大きな転機となるため、プロフィールの申請と楽曲のピッチは必ず行いましょう。
さらに、Spotify for Artistsは常に新しいプロモーションツールを追加しています。プロフィールを申請すれば次のような機能も利用できます。
- 楽曲にSpotify Canvas動画を追加
- 楽曲に歌詞を追加
- Spotifyの有料プロモーションツールを利用
- Spotifyの分析ツールを利用
- リリース前にプリセーブキャンペーンを実施
- ストリーミング収益を確認
Spotifyでの音楽プロモーションについては、より詳しい記事も用意しています。プラットフォームをフル活用したい方はぜひチェックしてください。
Spotifyのプレイリストに載る方法を学び、すぐに実践できるヒントを手に入れましょう。
5. Instagram・TikTokなどSNSで積極的に活動する
音楽プロモーションの現場で最も実践的な活動の場となるのがSNSです。音楽の公開やストリーミングサービスへのアップロードといった基本的な作業を終えたら、プロモーションの中心はほとんどSNS上で展開されることになります。
各プラットフォームごとに特徴やクセがあるため、SNSでの音楽プロモーションについて語れることは数え切れないほどあります。その中でも大切なポイントのひとつは、アカウント名(ハンドルネーム)をプラットフォーム間で統一することです。そうすればファンが迷わず見つけやすくなります。さらに、現在SNSでもっとも人気のあるコンテンツ形式は縦型動画です。Instagramのストーリーズやリール、TikTok、さらにはSnapchatにもフィットするため、縦型動画を活用することが強力なプロモーションにつながります。
6. アーティストやインフルエンサー、ブロガーとつながる
同じジャンルのアーティスト、インフルエンサー、ブロガー、プロデューサーと関係を築くことは、自分の音楽をより多くのファンに届ける強力な方法です。地元で活動している刺激を受けるアーティストに積極的に声をかけ、つながってみましょう。ファンにそのアーティストを紹介したり、投稿にコメントしたり、できる限り交流することが大切です。
フォロワーを持つアーティストやインフルエンサーに名前を覚えてもらえれば、面白いコラボレーションにつながったり、一緒にライブで演奏する機会を得られるかもしれません。
ニューヨークのA$APクルーやストックホルムのYung Lean率いるDrain Gangのように、志を同じくする仲間たちが集まり、互いの音楽を広め合いながら成功へとつながった事例もあります。協力し合い、コラボし、互いのオーディエンスに届けることでキャリアは大きく前進します。
7. ミュージックビデオや映像コンテンツを活用する
ミュージックビデオは90年代にMTVが普及して以来、アルバムリリースに欠かせない要素となってきました。
現在では、シングルごとにミュージックビデオを制作するのは音楽プロモーションの基本であり、1〜2本作るのは最低限と言えます。実際には、従来のミュージックビデオに限らず、さまざまな形式の映像コンテンツを発信するアーティストが増えています。
例えば、ライブ演奏を収録して公開すれば、ファンは生のサウンドを体感でき、次のライブへの期待感を高められます。
Vlogスタイルの投稿やTikTok向けの短い映像も、SNSでのリーチを広げる効果的な方法です。また、YouTubeやInstagramにアップロードする際、楽曲やアルバムに合わせたビジュアライザーを添えるだけでも、曲に視覚的な魅力を加えることができます。
映像制作は時間のかかる作業ですが、リターンは大きいものです。メッセージを明確にし、アーティストの美学を表現し、長く記憶に残る印象を作ることができます。ミュージックビデオ、ライブ映像、シンプルなビジュアライザーなど、どの形式でも構いません。音楽プロモーションに映像コンテンツを積極的に取り入れてみましょう。
LANDR Networkでアーティストやデザイナー、業界のプロとつながろう
8. ウェブサイトとメーリングリストを立ち上げる
ウェブサイトは自分らしさを存分に表現できる場です。デザインや雰囲気を自由に決められるので、音楽やブランド、美学を打ち出す絶好の機会となります。
トップページには楽曲やミュージックビデオを配置し、プレス掲載、ライブ情報、告知などをまとめるページを用意するのも良いでしょう。
また、ウェブサイトはグッズ(レコードやTシャツなど)やデジタル音源を販売する場としても機能します。まるで自分専用のレーベルショップのような役割です。購入しない訪問者に対しては、ニュースレターやメーリングリストへの登録を勧めておけば、イベント情報や新作グッズの告知を継続的に届けられます。
さらに、興味を持った人やメディア関係者が直接コンタクトできるよう、連絡先ページを忘れずに設置しておきましょう。
9. プレスキットをラジオやメディアに送る
音楽メディアはプロモーションにおいて強力な力を持っています。小規模な音楽メディアからの掲載であっても、音楽をより広いリスナーに届ける大きなきっかけとなります。
ただし、誰にアプローチするかと同じくらい、どのように連絡するかも重要です。
取材依頼や掲載依頼には注意点がありますが、基本的には自分のウェブサイトに電子プレスキット(EPK)を用意しておくと効果的です。
プレスキットには、記事やインタビュー、映像を作成するのに必要な情報をまとめておきましょう。リリースへのリンク、写真、ミュージックビデオやライブ映像などを含めるのがおすすめです。
また、アーティストとしてのビジョンを書いたプロフィール、経歴や活動の目標を掲載し、代表的なライブ、レビュー、受賞歴なども紹介してください。特に、人々の関心を引くエピソードがあれば積極的に盛り込みましょう。音楽を始めるきっかけとなった出来事や、地域社会に還元する思いなど、ストーリー性のある情報は大きな魅力になります。
誰にアプローチすべきか
音楽ブログは、音楽シーンにおける最も影響力のあるキュレーターのひとつです。The FADER、Spin、Pitchfork、Stereogumといった大手メディアは、これまで数え切れないほどのアーティストをメインストリームに押し上げてきました。ただし、これらに取り上げられるにはパブリシストの力が必要な場合が多いのも事実です。とはいえ、小規模な音楽ブログであっても驚くほどの影響力を持つことがあります。
しっかりとしたプレスキットを用意できたら、自分の音楽に関心を持ってくれそうなメディアに送ってみましょう。自分と近いジャンルやスタイルのアーティストを取り上げているブログを探し、連絡先を調べてみてください。また、大学ラジオのようにインディペンデントな楽曲を積極的に流してくれるラジオ局に送るのも有効です。
さらに、新人アーティストからの応募を受け付けているフェスもあります。出演に適したフェスがあれば、積極的にプレスキットを送ってみましょう。
ただし、現実的に考えることも大切です。音楽メディアは数多くのアーティストから連絡を受けているため、誰にアプローチするかは慎重に選びましょう。SNSや地域の音楽シーンで存在感を示し、ライターやメディア関係者と実際に関係を築くことの方が、単なる一斉送信メールよりも確実な結果につながります。
10. できるだけ多くライブに出演する
地元の音楽シーンに積極的に関わることは、オーディエンスを広げ、音楽業界との重要なつながりを作るために大きな力を発揮します。数多くの新進アーティストは、SNSでの発信と地域シーンでの強固な人脈作りを組み合わせて成功をつかんできました。
ライブセットを組んで、自分の名前をイベントのブッキングリストに載せてもらう方法を探しましょう。地元のブッカーに直接連絡を取り、一緒にイベントを企画するのも良い方法です。
例えば、アルバムやシングルのリリースイベントを企画すれば、ライブに対する期待や話題性を簡単に高めることができます。
ステージに立った際は、SNSアカウントを観客に紹介し、フォローをお願いしましょう。名刺やカードを持参しておけば、終演後に話しかけてきたファンに渡すこともできます。
もちろん、魅力的なライブを実現するには努力、練習、スキルの磨き上げが必要です。しかし、継続してブッキングを重ねていくための第一歩を作り上げれば、その努力は何倍にもなって返ってきます。
音楽プロモーションを始めよう
音楽活動はワクワクする冒険であり、その中でプロモーションは欠かせない要素です。
大切なのは音楽を発表することだけでなく、ファンとつながり、コミュニティを築き、自分だけのサウンドとストーリーを共有することです。
Spotifyでのオーディエンス拡大、SNSというダイナミックな世界での活動、音楽コミュニティの中で存在感を示すこと──そのすべてが新しいリスナーやファンを見つける手助けになります。
自分の音楽プロモーション計画を立て、世界に音楽を届けましょう。
LANDRで音楽をプロモーションする
ストリーミングサービスへの配信、プロモーションサービスなどを活用し、キャリアを前進させましょう。